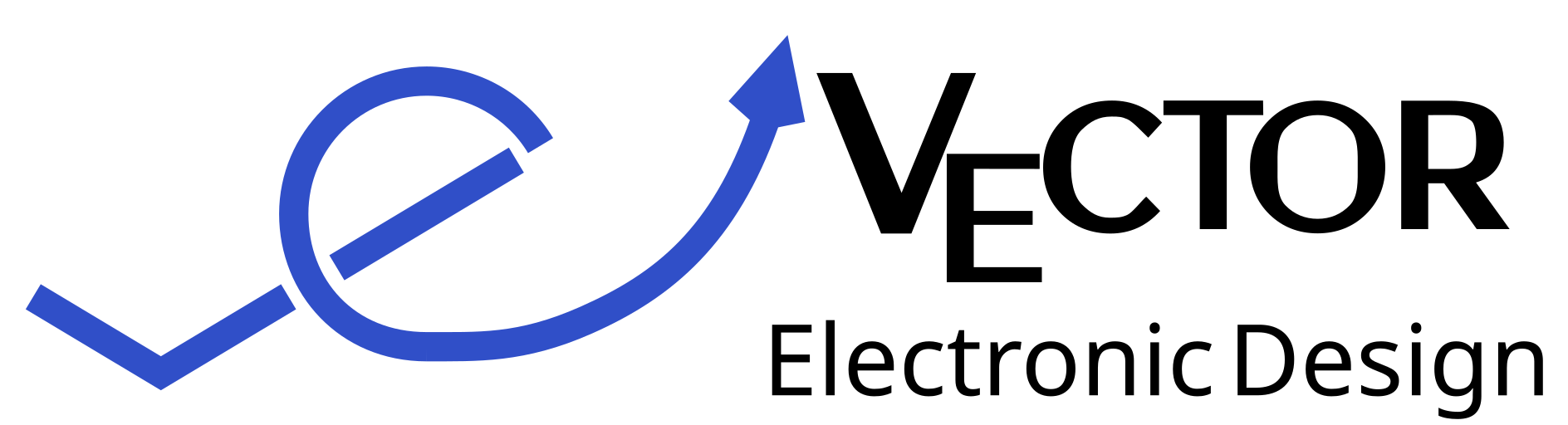【技術ノート】オシロスコープの受動プローブについての小知識
オシロスコープでよく使う受動(パッシブ)プローブの使い方や注意点について、Q&A形式で整理した記事をnoteに公開しました。測定精度を高めるための基本から、GND接続の工夫、プローブの補正や安全な接地方法までポイントをまとめています。 詳しくは以下のnote記事をご覧ください。
記事の主な内容
- パッシブプローブの基本構造とx1/x10切替の違い
- なぜ基本的にx10設定を使うべきか(入力抵抗・容量・帯域の違い)
- x1プローブと普通の同軸ケーブルの違い(抵抗線による過渡特性改善)
- GNDを1本だけ接続した場合の問題点(ループ面積拡大・波形乱れ)
- GNDリードを短くする方法(GNDスプリングやリードアダプタの活用)
- 50Ω信号測定時はプローブではなく同軸ケーブルを使用すること
- プローブ調整(トリマコンデンサを使い矩形波を正しく観測できるように調整)
- オシロスコープのアース接続の重要性(接地しないと数十V浮いて感電や機器破損の危険がある)
投稿者プロフィール

- ベクター電子設計事務所代表
最新の投稿
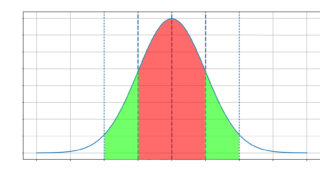 お知らせ2026年1月15日【技術ノート】測定と誤差、不確かさ
お知らせ2026年1月15日【技術ノート】測定と誤差、不確かさ お知らせ2026年1月5日新年あけましておめでとうございます。
お知らせ2026年1月5日新年あけましておめでとうございます。 お知らせ2025年12月22日年末年始期間中の対応についてのお知らせ
お知らせ2025年12月22日年末年始期間中の対応についてのお知らせ お知らせ2025年12月5日【技術ノート】電流の各種測定方式と特徴の解説
お知らせ2025年12月5日【技術ノート】電流の各種測定方式と特徴の解説